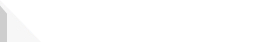デジタル印刷が静かに従来の印刷を圧迫していることをご存知ですか?
公開日時:
2025-01-23
もし、版を必要としないデジタル印刷技術がアメリカのチェスター・カールソンが1938年に静電イメージング原理を用いて最初のコピー機を作ったことから始まったとするなら、デジタル印刷が広く受け入れられ、新たな市場のホットトピックとなったのは2016年のドイツ・ドゥルーバ印刷展以降であるべきです。なぜなら、ハイデルベルグや小森などの伝統的な印刷機器製造企業はほぼ例外なくこの分野に参入しており、これは彼らがデジタル印刷の次のステップの発展を期待していることを意味します。実際、ここ数年、デジタル印刷はさまざまな分野での応用が増減しており、その根本的な理由は市場が変化しているからです。例えば、最初に可変データ印刷を応用したのは...
もし、印刷版を必要としないデジタル印刷技術が、アメリカのチェスター・カールソンが1938年に静電イメージング原理を用いて最初のコピー機を作ったことから始まったとするなら、デジタル印刷が広く受け入れられ、新たな市場のホットトピックとなったのは2016年のドイツ・ドゥルーバ印刷展以降であるべきだ。なぜなら、ハイデルベルグ、小森などの伝統的な印刷機器メーカーはほぼすべてこの分野に参入しており、これは彼らがデジタル印刷の次の発展を期待していることを意味する。
実際、この数年、デジタル印刷は各分野での応用において上昇と下降があり、その根本的な理由は市場が変化しているからである。例えば、可変データ印刷を生産に最初に応用したチケット業界は、電子請求書の台頭により下降しており、この傾向は逆転不可能である。しかし、インクジェット印刷は建築装飾、繊維染色、ラベル印刷分野で急速に発展しており、パッケージ印刷は次のホットトピックになる可能性が高い。
これらすべては技術の進歩とも関係があり、中国人の生活水準が温飽から小康へと移行したこととも関係がある。
この変化はすべての印刷マネージャーの注目を集めており、最も顕著な表れはデジタル印刷フォーラムに参加する伝統的な印刷企業の代表者が増えたことである。彼らはこの変化を理解し、時代の発展に遅れないようにしたいと考えている。
個性ニーズを満たす
これがデジタル印刷の最大の利点である。
オンデマンド、可変、即時がデジタル印刷の利点である。物資が相対的に不足し、デジタル印刷の品質も向上する余地がある時期には、これらの特徴は客観的に制約を受けており、応用分野は相対的に限られている。
しかし、国民が温飽から小康へと移行した後、彼らは生活を楽しむ資本を持ち始め、自身の個性を表現し、自身の価値を示すことを求めるようになった。また、デジタル印刷機器は幅面、速度、品質、承印媒体などの面で絶えず突破を続けており、このようなデジタル技術と共に成長した新しい印刷生産プロセスが進出する分野は増え続けている。ラベル印刷は間違いなく近年デジタル印刷が急速に発展している分野である。
近年ラベル印刷は比較的早くデジタル印刷技術を使用するようになっており、それはラベル自体の市場特性とも関係があり、また社会全体が一定の段階に達したこととも関係がある。
ラベルは商標と密接に関連しており、ラベルを使用するためにはまず商標登録を経る必要がある。商標は商品を明確に示し、消費者に鮮明なブランド記憶を残すためである。しかし、一度商標登録されたからといって必ずしもラベルを使用するわけではなく、ラベル使用の有無は製品属性によることが多い。例えば食品や飲料、衣服などでは一般的にラベルが使用される。
しかしそれでもなお、ラベルの形式や媒体には依然として違いがあり、プラスチックボトルラベルや紙製タグなどもあれば、一部のブランド家具では直接家具表面にラベルを焼き付けることもある。我が国では歴史的な計画経済から市場経済へ移行した後、物質的な豊かさと共にラベルの量も増加し続けており、更なる成長傾向も見られる。
中国印刷及び設備器材工業協会によって編纂された『中国印刷産業技術発展ロードマップ』によると、2014年までに我が国のラベル印刷年産値は330億元人民元に達し、その年の総印刷産値の3%を占めている。その中で、不干渉ラベル印刷量は44億平方メートルであり、中国全国で6000社以上の企業がラベル印刷に従事し、その従業員数は約6万人である。これらの数字は明確に我が国におけるラベル印刷がかなり大きな印刷分野であることを示している。
社会発展と一定段階に関連しているとは、人々が個性を主張するニーズへの要求が温飽から小康へと移行したことによって引き起こされたことを指す。
その理論的根拠はアメリカ心理学者マズローによって1943年に提唱された人間需要5つの階層からなるピラミッド理論(図1参照)である。温飽段階では、人々は生理的及び安全ニーズを追求し、生存するためである;小康段階に入ると、人々は社会的及び尊重ニーズを追求する能力を持ち、その目的は帰属感を求めることであり、現在の中国はまさにそのような段階にある。
ゴールドマン・サックスアジア中国統計局によって2013年中国人均収入状況にもとづいて作成された富裕分配表(図2参照)によれば、その年には我が国ですでに48.2%の労働人口が小康区域内で収入水準に達していた。また2015年CHFS調査データによれば、その年中国中産階級数は2.04億人となり、その富総量は28.3兆元となりアメリカや日本を超えて世界一位となった。このことはもちろん人口基数との関連もある。
国民経済条件の改善によって消費財への個性追求が可能になり、それによって個性を主張できるラベル印刷も注目されるようになった。
近年デジタル印刷はラベル分野で
急速に成長している。
事実として証明されていることは、個性化された製品は人々の心情ニーズを満たすため消費を促進できるということである。例えば:贈り物受取者名入りの商品ラベルや、新婚夫婦名入りのお菓子などは意外な驚きを与えるだろう。
さらに例えば:山東緑愛社が提供する広告付きキャンディ包装では、人々はキャンディのおいしさを楽しむだけでなく広告宣伝効果も得られる(図3参照);自分自身の願望に合った異なる文句入りTシャツを着ることで、自身の個性や好みも一定程度表現できる。
さらにデータによれば、個性化されたラベルは製品販売を促進できるということだ。コカ・コーラ社は最初に個性化されたラベルを導入したブランドであり、この大胆な試みは国際ブランド企業としての胆略だけでなく、本当にコカ・コーラにも利益をもたらした。
関連データによれば、2013年コカ・コーラ社はニックネームボトル(図4参照)という試みとして、「親友」「小さな女児」「食いしん坊」など様々な流行するニックネームを製品に適用した。この試みは元々統一された商標制作よりも費用増加につながるだろう。しかし個性化商標導入によって、その年コカ・コーラ社の市場売上高は前年より20%増加した。この背景には炭酸飲料への批判的意見もあったことも忘れてはいけない。
成功した試みは同社がこの取り組みを継続する自信につながり、2014年には歌詞ボトルを導入し売上高再び9%増加した。その後2015年にはセリフボトル、2016年にはゴールドメダルボトル、2017年には秘密ボトルなども導入された。当然ながらラベル改革が製品販売にもたらす利益さえあれば企業側も喜んで取り組むだろう。
まさしくコカ・コーラ社によって導入された個性化されたラベルによって、多くの企業も積極的についてきた。「味全」は「消費者との対話モデル」を構築し、「理由ボトル」「HI(ハイ)ボトル」「文字合わせボトル」を次々と導入した;「伊利」や「康師傅」は告白ボトル、「統一グループ」は小茗同学なども導入した……さらに「江小白」(図5参照)や「オレオ」(図6参照)などもあり、このすべてが証明していることは消費者との距離感を縮めて消費者にも製品以外の追加体験を提供できれば、新たな売上や利益につながる可能性があるということである。
個性化ラベルの誕生と成長は、デジタル印刷技術がラベル印刷分野での応用を促進するのは当然のことです。なぜなら、デジタル印刷は短版印刷や可変印刷に適しているからです。そのため、山東緑愛はHP社が製造したIndigo 20000の国内初のユーザーとなり、多くの国内ラベル印刷企業もさまざまな仕様のデジタル印刷機を導入しました。
ラベル印刷の発展の歴史を振り返ると、同一ブランド内での多様な仕様や小ロットの特徴が、一部の先見の明を持つ企業リーダーが早期にデジタル印刷機を導入する決定要因となったことがわかります。国内の同業者の中で高い影響力を持ち、精密管理を特徴とする上海小林印務公司は、デジタル印刷とオフセット印刷を組み合わせてラベル印刷を行っています。
確実に言えることは、個性化ラベルの市場需要は、中国の一人当たり年国民所得がさらに向上するにつれて同時に増加する可能性があるということです。したがって、デジタル印刷製品のコストパフォーマンスをさらに向上させる限り、従来の印刷からデジタル印刷によるラベル印刷への移行量も同時に増加するでしょう。
デジタル印刷はラベル印刷分野で
気候形成の二大要因
ドイツの哲学者ヘーゲルが言ったように、「存在するものは合理的である」。近年、デジタル印刷がラベル印刷分野で急速に発展できた理由は、自身にある理由が必然的に存在します。これは、社会発展によって中国の一人当たり国民所得が小康レベルに達し、人々が個性を追求する物質的基盤を持つようになったことに加え、以下の二つの理由も考えられます。
第一に、比較的高い粗利益率が企業にデジタル印刷の比較的高い生産コストを支える助けとなっています。
疑う余地なく、デジタル印刷設備および消耗品の高い海外依存度は、製品が今でも良好なコストパフォーマンスを欠いている原因となっています。現在、消費者がデジタル印刷製品による便利さを知らないわけではなく、むしろ比較的高い市場価格が消費者にお金を使う際に躊躇させていると言えます。デジタル印刷で完成した書籍の価格はオフセット印刷で完成した書籍よりも遥かに高く、このことは消費者と生産企業との間で慎重な検討や価格比較を促す要因となっています。
しかし、ラベル印刷は比較的高い粗利益率を持っているため、彼らはデジタル印刷という新しい生産技術を受け入れる際、その長所に目を向けることができ、個性化ラベル印刷におけるデジタル印刷の市場発展トレンドを見ることができる能力も持っています。また、従来の印刷技術よりも若干高い新たなコストを負担する能力もあります。
さらに、ラベル印刷は感覚的には大量ですが、版を組み合わせた後に実際に印刷される部数は相対的に少ないため、小ロット製品には需要に応じたデジタル印刷技術が適しています。市場変化のペースが加速している今日では、デジタル印刷は即時性や可変性、需要対応で顧客の要求を満たすことが容易です。
第二に、高い環境保護要求が企業に生産方式の転換を迫っています。
ラベル製品は少量多品種という特性から歴史的には主に凸版印刷方式で完成され、その後柔版印刷へと転換されました。「中国印刷産業技術発展ロードマップ」の「ラベル印刷産業」章による分析では、現在国内ラベル印刷市場シェアはそれぞれ:凸版70%~75%、柔版10%~12%、オフセット7%~8%、デジタル2%~3%、その他5%~7%とされています。2014年のこのデータは、この数年間で大きな変化があると予想されます。
元々凸版から柔版への移行には環境保護が重要な理由ですが、実際には柔版印刷の版作成コストが相対的に高く、印刷精度もあまり高くないため、それが急速な発展を制約しています。静電イメージング原理によるデジタル印刷では有毒有害ガス排出が存在しない(または非常に少ない)ことを認識した多くの企業が新しいデジタル印刷技術を採用することを選択しています。
近年、デジタル印刷技術は建築装飾や繊維染色分野にも迅速に進出し、生産モデルも従来の生産計画から需要ベースへと変わりました。これは環境保護にも関係しています。販売計画による生産方式では製品販売不振による廃棄損失を回避でき、大幅に事前製造資金投入も削減できます。これは短版書籍印刷がデジタル印刷へ進む上で参考になる意義があります。
指摘すべき点は、現在まで、高品質なデジタル印刷設備はほとんど輸入に依存しており、設備および消耗品の市場価格も高く、またデジタル印刷設備の更新速度も速いため、短期間内に投資回収できない場合、本当に設備供給業者のために働くリスクがあります。そのため、デジタル印刷設備と消耗品の国産化を加速させることは業界全体の健全な発展に関わる重要な課題です。
注意すべき点として、技術進歩とともにラベル素材も変わる可能性があります。
ラベル印刷はパッケージング業界になくてはならない重要な部分であり、デジタル印刷が迅速にラベル印刷分野へ進出することは技術革命であるだけでなく、企業アップグレード転換過程で新興勢力としてチャンスを捉えて関連分野へ進出する可能性も示しています。
例えば、生活になくてはならない写真プリントは従来の銀塩プリントからデジタルプリントへと移行しています。写真プリント専門家によれば、この市場規模は2016年には3169億元人民币にも達しており、このような新興市場でデジタルプリント生産者が無関心でいるとは考えられませんか?
デジタルプリントが迅速にラベルプリント分野へ進出したことを喜ぶ一方で、自覚すべきなのはラベル自体も前進しているということです。スマートラベル(RFID)はその一例であり、一部領域では従来の紙製ラベルを完全に置き換える可能性があります。最も明らかな例として、多くの従来型紙製チケットがチップ埋め込み型スマートチケットへと置き換えられています。
それでは技術進歩とともに従来型紙製ラベルが他の新しい素材によって置き換えられる可能性がありますか?もちろん、それが全面的な置き換えとは限りません。しかし、新技術や新しいラベル素材の登場によって、生産プロセスも再転換される可能性があります。
"十三五"期間中には凹版・凸版・平版・孔版・デジタルプリントという5つの技術が市場ニーズによって再構成されます。それらは互いに融合し合い、新興勢力として位置づけられるデジタルプリント比率も持続的に上昇します。デジタルプリント設備と消耗品が国産化された後、その発展速度は必ずさらに加速します。我々はデジタルプリントがすでにラベルプリント分野で活躍していることを嬉しく思い、更なる輝かしい未来への期待も寄せています。
キーワード:
前のページ
次のページ
前のページ:
次のページ: